NEWS&TOPICS
労働基準関係法制研究会報告について
2025年02月05日
労働基準法等の見直しを検討するため有識者で構成された厚生労働省の労働基準関係法制研究会(以下「研究会」といいます。)において、報告書がまとめられ、2025年1月8日に公表されました。この報告書をもとに、今後労働基準法改正に受けたより具体的な議論が労働法制審議会で議論されることとなります。
そこで、今回は研究会においてどのような検討がなされたのか、主要な点についてみていきます。
より詳しく内容を知りたい方は、下記のURLで報告書が確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11402000/001370269.pdf
◆過半数代表者
就業規則届出に当たっての意見聴取や労使協定の締結の相手方となる過半数代表者について、次のような議論がありました。
・使用者による情報提供
過半数代表者が事業場の労働者の意見を集約するにあたり、労働者名簿や、誰が労使協定の影響を受けるものであるかの情報などを、過半数代表者に提供することを使用者の責務とすべきであるとされました。
・過半数代表者の任期
任期を定めて過半数代表者を選出することは、現行法上も許されているが、余りにも長期の任期を設定することは問題があることから、上限等をガイドラインで明示することや、労使協定の有効期間に合わせた期間等にする提案などがなされました。
◆テレワーク等の柔軟な働き方・使用者による情報提供
過半数代表者が事業場の労働者の意見を集約するにあたり、労働者名簿や、誰が労使協定の影響を受けるものであるかの情報などを、過半数代表者に提供することを使用者の責務とすべきであるとされました。
・過半数代表者の任期
任期を定めて過半数代表者を選出することは、現行法上も許されているが、余りにも長期の任期を設定することは問題があることから、上限等をガイドラインで明示することや、労使協定の有効期間に合わせた期間等にする提案などがなされました。
テレワーク等の柔軟な働き方との関係で、次のような議論がありました。
・フレックスタイム制
テレワークを行う日と通常勤務する日がある場合、現行法ではフレックスタイム制を部分的に適用することができないため、テレワークを行う日だけにフレックスタイム制を適用することはできず、適用するか適用しないかの二者択一となっています。これを、部分的にフレックスタイム制を適用できるように改善することが提案されました
・テレワーク時のみなし労働時間制
テレワークは、仕事と家庭生活が混在しうるため、実労働時間を問題としない「みなし労働時間制」(実際何時間働いたかに関わらず労使協定等で定めれられた労働時間働いたとみなす制度)が望ましいと考える労働者に選択できる制度を、実効的な健康確保措置を設けたうえで、在宅勤務に限定した新たなみなし労働時間制を設けることが提案されました。
◆連続勤務日数の制限・フレックスタイム制
テレワークを行う日と通常勤務する日がある場合、現行法ではフレックスタイム制を部分的に適用することができないため、テレワークを行う日だけにフレックスタイム制を適用することはできず、適用するか適用しないかの二者択一となっています。これを、部分的にフレックスタイム制を適用できるように改善することが提案されました
・テレワーク時のみなし労働時間制
テレワークは、仕事と家庭生活が混在しうるため、実労働時間を問題としない「みなし労働時間制」(実際何時間働いたかに関わらず労使協定等で定めれられた労働時間働いたとみなす制度)が望ましいと考える労働者に選択できる制度を、実効的な健康確保措置を設けたうえで、在宅勤務に限定した新たなみなし労働時間制を設けることが提案されました。
現行法では、法定休日は1週1休が原則とされていますが(労働基準法35条1項)、変形休日制を導入し4週4休(同条2項)とすることで、最大48日連続勤務が可能(ただし別途時間外割増等が発生する可能性有)となっています。
報告書では、精神障害の労災認定基準を踏まえて、「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を明記すべきと提案されました。
◆年次有給休暇報告書では、精神障害の労災認定基準を踏まえて、「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を明記すべきと提案されました。
年次有給休暇を取得した日の賃金は、①労働基準法12条の平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③健康保険の標準報酬月額の30分の1(③は労使協定が必要)のいずれかにより支払うこととなっています。
報告書では、②の通常の賃金によることを原則とすることが提案されました。
◆副業・兼業の割増賃金報告書では、②の通常の賃金によることを原則とすることが提案されました。
厚生労働省の現在の見解では、副業・兼業を行う場合、本業との労働時間を通算して割増賃金を支払う必要があるとされています。
しかし、フランス・ドイツ・オランダ・イギリスでは、副業・兼業を行う場合の割増賃金の支払いについては労働時間の通算を行う仕組みになっていません。
また、副業・兼業を行う場合に割増賃金の支払いについて労働時間の通算が必要であることが、本業の企業が副業・兼業を許可することを抑制したり、副業・兼業を希望する他社の労働者を雇用することを困難にしているとの指摘があります。
報告書では、副業・兼業を行う場合の割増賃金の支払いについては労働時間の通算を要しないように、制度改正を行うことが提案されています。ただし、この場合でも、労働者の健康確保のための労働時間の通算は維持すべきとされている点は、留意が必要です。
しかし、フランス・ドイツ・オランダ・イギリスでは、副業・兼業を行う場合の割増賃金の支払いについては労働時間の通算を行う仕組みになっていません。
また、副業・兼業を行う場合に割増賃金の支払いについて労働時間の通算が必要であることが、本業の企業が副業・兼業を許可することを抑制したり、副業・兼業を希望する他社の労働者を雇用することを困難にしているとの指摘があります。
報告書では、副業・兼業を行う場合の割増賃金の支払いについては労働時間の通算を要しないように、制度改正を行うことが提案されています。ただし、この場合でも、労働者の健康確保のための労働時間の通算は維持すべきとされている点は、留意が必要です。
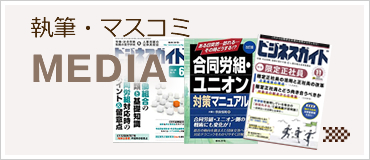


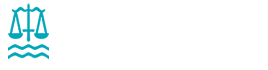

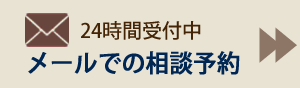
場合によっては、これまで個人事業主とされていた者の一部が労働者となる可能性もある議論であることから、今後の推移を注視していく必要があります。